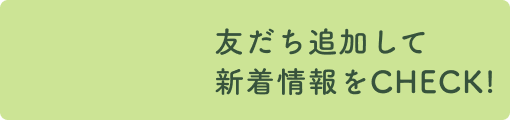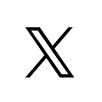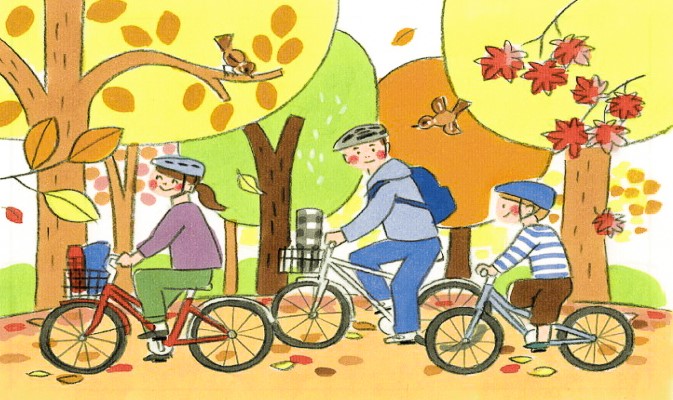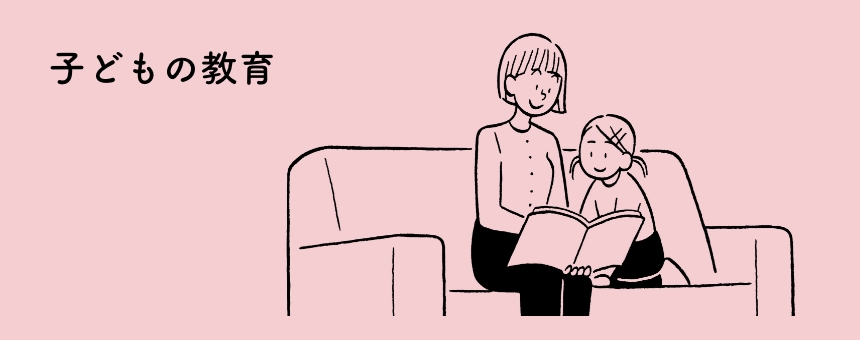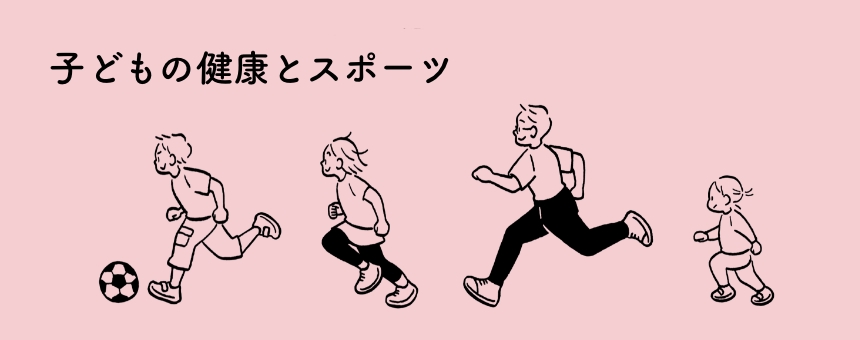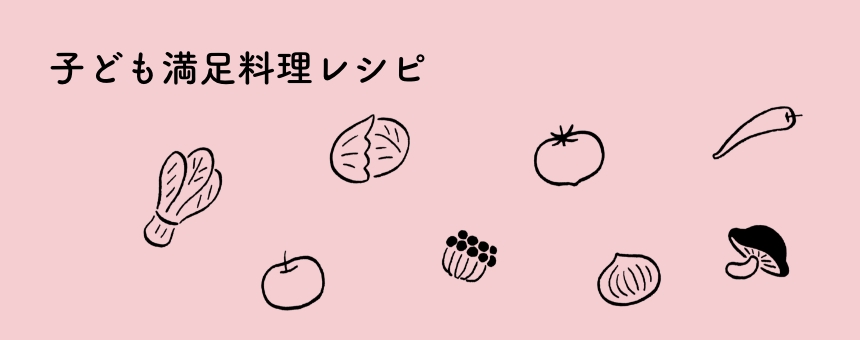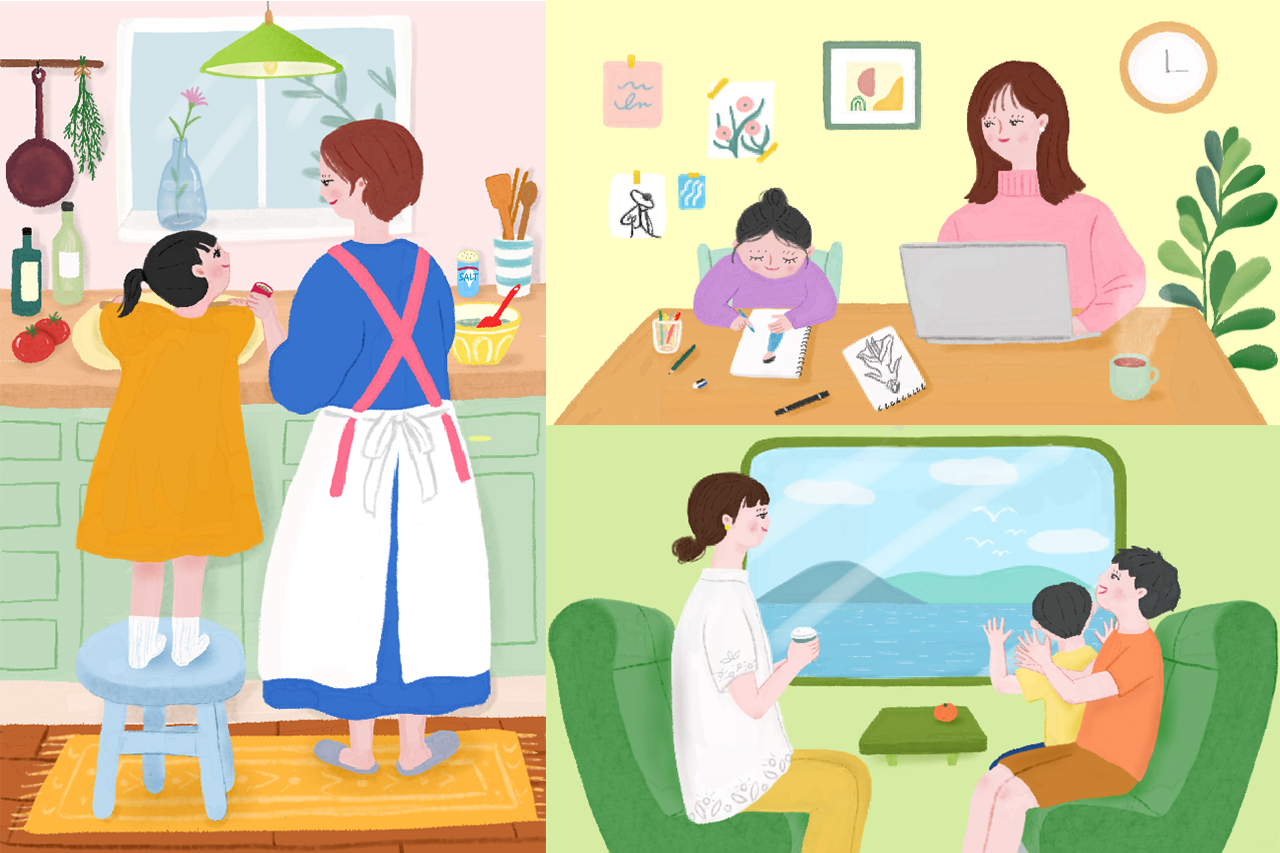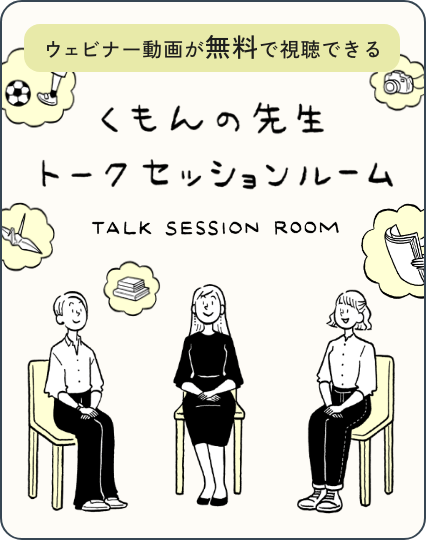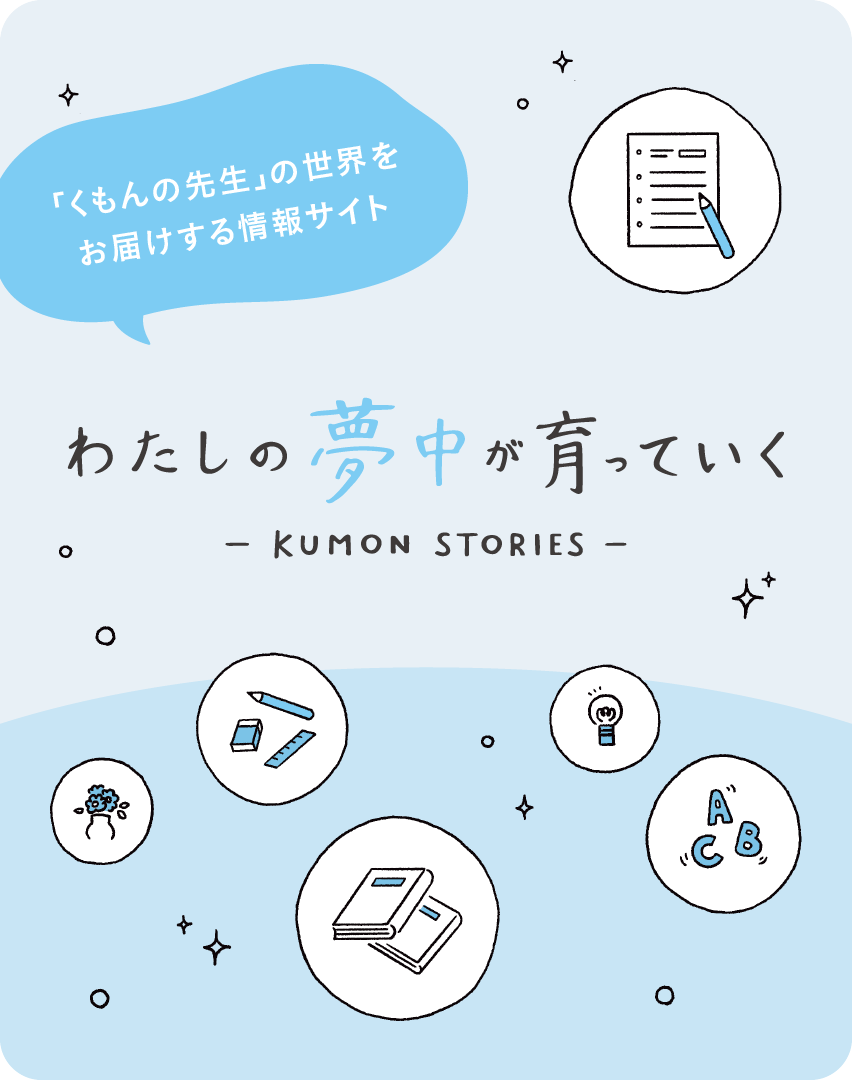子どもに合った歯ブラシの選び方や、仕上げみがきの卒業時期を知っていますか? 後編では、子どもの清潔な口内環境や歯の成長を促すうえで知っておきたい基礎知識、さらに歯ブラシにプラスして使いたい歯みがきのお助けアイテムなどをご紹介します。
子どもの虫歯予防につながる正しい歯ブラシ選び

「子どもに正しい歯みがきを身につけさせるためには、実は歯ブラシ選びの時点から意識しておくことが重要です」
子どもの口腔機能の育成に関するスペシャリストとして臨床、教育、研究に従事している、鶴見大学歯学部小児歯科学講座教授の朝田芳信先生に、歯ブラシを選ぶ際にチェックしたい3つのポイントを教えてもらいました。
ポイント➀歯をみがくブラシの部分“ヘッド”
「乳歯は下の前歯から生えてくるので、1~2歳は、下の前歯2本分くらいのヘッドの大きさの歯ブラシを選びましょう。乳歯が生えそろったら、下の前歯4本分ほどのヘッドが最適です。
乳歯と永久歯が混じっているときは、乳歯の奥歯2本分、永久歯が生えそろったら下の前歯4本分のヘッドの大きさの歯ブラシを選びましょう。
子どもの口や歯に合っていない歯ブラシを使っていると、十分に汚れを取ることができません。定期的にサイズを見直し、口や歯の成長に合ったものを選ぶことが大切です。また、毛先が大きく開いてしまうと、清掃効果が40%ダウンするといわれています。毛先が開いてきたらすぐに交換することも大事です」
ポイント➁持ち手“ハンドル”
「子どもが歯ブラシをしっかり握るためには、ハンドルは太めの楕円形タイプがおすすめです。手にフィットしていないと、握ったときに力が入らず、外からはきちんとみがけているように見えても、歯に歯ブラシを当てたときにすべってしまい、みがけていないのです。ハンドルを握って、歯にきちんと歯ブラシの毛先が当たっているかどうかを確認してあげるといいでしょう」
ポイント③ヘッドとハンドルをつなぐ部分“ネック”
「ネックには、長いものと短いものがあり、長いほうが口の奥までヘッドが届きます。6歳臼歯が生え始めたら、奥歯をしっかりみがくためにも、ネックの長いものを選ぶといいでしょう」
子どもの虫歯を予防するポイントは?
それでは、ここからは日々の生活の中で気をつけたいことや手軽に取り入れられるお助けアイテムなど、具体的な予防法について考えていきます。
口呼吸を防ぐ
「口呼吸は虫歯や歯周病になりやすくなるだけでなく、風邪やインフルエンザなどの感染症にもかかりやすくなる」と朝田先生。
「口呼吸をしていないかを確認するには、子どもがぼーっとしているときに口が開いていないかを見るといいでしょう。口が開いていれば口呼吸になっているので、指で下唇を少し上げてあげましょう。
また、口呼吸をしていると、上の前歯の裏側の歯茎が乾燥しやすくなるため、歯みがきの際に出血することがあります。さらに、子どもに舌をべーっと出してもらい、舌の表面に“舌苔(ぜったい)”と呼ばれる白い苔のようなものがポツポツとついていたら、口呼吸の可能性があるといえるでしょう。
舌苔は、舌みがきで取り除くことができます。舌みがきは、舌の奥から手前に、歯ブラシでやさしくなでるように5回程度みがくだけです。強くみがいてしまうと、舌の上にある味覚を感じるセンサー“味蕾(みらい)”を傷つけてしまうので、やさしくなでるのがポイントです。
舌苔がなくても、舌みがきは口呼吸の予防になるので、歯みがきの最後に取り入れて習慣にするといいでしょう」
おやつの習慣を見直す
おやつが習慣となっている子どもは多いのではないでしょうか。おやつは3食で摂りきれない栄養を補給するために重要なものですが、食べるものによっては、虫歯につながってしまうかもしれません。
前編でもお伝えしているとおり、口内の細菌が虫歯菌を生み出す際のエサになっているのが糖質。おやつの時間にスナック菓子や甘い飲み物といった糖質を多く含むものを摂取してしまうと、虫歯菌を生み出すエサを余計に口に入れてしまっているということなのです。
食べるものに加え、おやつを食べる時間や量にも注意したいところ。だらだらと食べ続けて常に口の中に糖があるという状態を避けるためにも、おやつの時間をしっかりと定めるのも効果的です。目安として、3歳までは1日2回、3歳を過ぎたら1日1回が適切とされています。おやつを摂りすぎてしまうと、朝昼夕の肝心の食事のタイミングで空腹にならず、しっかりとした栄養補給ができなくなりかねません。
しかし子どもにとってのおやつ=間食や補食、つまり“食事の一つ”という意味合いも持ちます。歯の健康を守りながら、成長に効果的なおやつになるよう心掛けましょう。おすすめは乳製品や野菜、フルーツなどがおすすめです。“おやつ=食べてはいけない”のではなく、適切な時間に適切なものを、量を決めて食べることを習慣化できるように、今のおやつが虫歯の原因になっていないか、見直してみるといいかもしれません。(*1)
シーラントやフッ素塗布を行う
子どもに合った歯ブラシを使うことが効果的だとお伝えしましたが、虫歯予防の観点でいうと、歯ブラシと一緒に使う歯みがき粉にも意識を向けてみましょう。その際に選びたいのが、フッ素入りのもの。フッ素は、虫歯の原因となる菌の働きを弱める効果があるため、歯みがきから摂取することで、日頃の虫歯菌の発達を抑える効果が期待できます。フッ素は歯みがき粉だけでなく洗口液(マウスウォッシュ)に含まれているものもあるので、手軽にできる方法から取り入れてみるといいでしょう。
フッ素と同様に意識したいのが、歯にコーティングをして溝を塞ぐことで、食べ物の残りカスの蓄積や細菌の侵入を防ぐシーラント。こちらは歯みがき粉などに入っているフッ素とは異なり歯科に行く必要がありますが、子どもの歯を守るために検討をしてみてもいいのではないでしょうか。(*2)
歯みがき後にデンタルフロスとぶくぶくうがいを取り入れよう

さらに朝田先生は、歯みがきにプラスすることで虫歯を予防してくれるお助けアイテムを教えてくれました。
「お子さんにデンタルフロスを使っていますか? 虫歯の原因となるデンタルプラーク(歯垢)は、歯みがきだけでは除去率が60%、デンタルフロスを使うと86%まで汚れが取れるといわれています。さらに、ブクブクうがいを加えることで、除去率は90%以上になります。
ですので、5~6歳で歯みがきがスキルアップしてきたら、デンタルフロスも取り入れるといいでしょう。ただ、一気にやるのは大変なので、段階的に教えてあげてください。子どものうちに習慣化しておけば、大人になったときの虫歯予防にもつながります」
定期的に歯科検診を受診する
定期的に歯の専門家である歯科医師による診療を受けるようにしましょう。プロから正しい歯みがきの方法を教わったり、クリーニングをしてもらうことで虫歯やその他の口内の問題を早期に発見し、治療することができます。(*2)
子どもの虫歯予防に関する、よくある質問
ここからは、子どもの虫歯予防に関する気になる質問を、朝田先生に答えてもらいました。
Q.歯みがき粉は何歳から?
A.3~4歳頃から
「歯みがき粉にはさまざまな成分が入っているため、ブクブクうがいができるようになる3~4歳頃から使うことをおすすめします。それまでは、何もつけずに歯をみがかせ、仕上げみがきの後、歯ブラシに市販されているフッ素のジェルやムースをつけて、歯面にまんべんなく塗ってあげるといいでしょう。
ただ、これは小児歯科としての考えであって、市販されている9割以上の歯みがき粉にはフッ素が含まれていることから、うがいができるかどうかに関係なく、もっと低年齢から少量ずつでも使っていいというのが、口腔衛生学を専門としている先生たちの考えです。ですので、かかりつけの歯医者さんにより意見は違うかもしれません。
なお、昔に比べ、子ども用歯みがき粉の安全性は高くなっているので、飲み込んでも問題ないといえるでしょう」
Q.仕上げみがきの卒業時期は?
A.大人と同じようにみがけるようになったら

「個人差はあるものの、一般的に仕上げみがきは、8歳頃までは必要だとされています。なぜなら、6歳臼歯が生え始めてからの2年間は虫歯になりやすいからです。
仕上げみがきを卒業できるチェックポイントは、肩やひじを動かさず、大人と同じようにブラッシングできているかどうかです。体を動かすことなく、固定した状態で歯みがきができるようになれば、歯ブラシがしっかり歯に当たっているので、仕上げみがきの卒業時期といえるでしょう」
Q.歯みがきをするベストなタイミングは?
A.夕食後から寝る前

「一日の歯みがきの中で最も大事なのは、寝る前です。けれど、寝る直前までバタバタしてしまい、寝る前の歯みがきはおろそかになりがちです。余裕をもって寝る前に歯みがきをするためにも、寝るまでの生活リズムの中に歯みがきの時間を作っておくことが大切です。寝る前が難しければ、夕食を終えた後でもいいでしょう。
また、歯医者さんには虫歯ができてから行くのではなく、トラブルがなくても3~4カ月に一度は行くことをおすすめします。というのも、歯の付着物が虫歯に移行するのに3~4カ月かかるので、そのインターバルで歯医者さんに行くと、虫歯の早期発見・治療にもつながるからです。
また、子どもには、歯医者さんは痛い思いをにしに行くところではないと伝えることも大切です」
まとめ
いかがでしたか? 後編では、歯ブラシや歯みがき粉の選び方といった日常生活で意識できる虫歯予防について、そして仕上げみがきの適切な卒業時期など、保護者が気になる疑問について紐解いてきました。日頃できることから意識して、子どもの歯の健康をこれからも見守っていきましょう。
この連載の他の記事はこちら
取材・文:サカママ編集部 取材協力:朝田芳信(鶴見大学歯学部小児歯科学講座教授) 参考文献:朝田芳信著『ドクター朝田の 間違いだらけの子どもの歯みがき』(春陽堂書店)