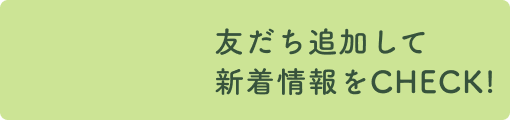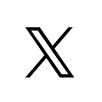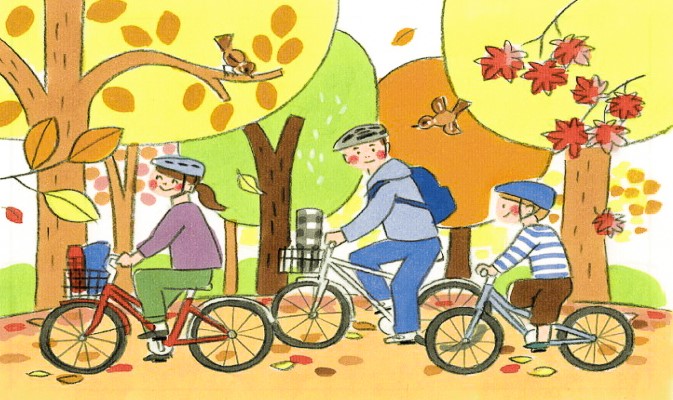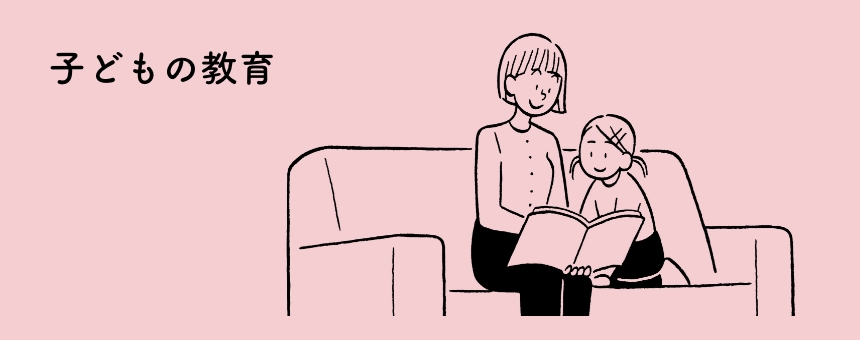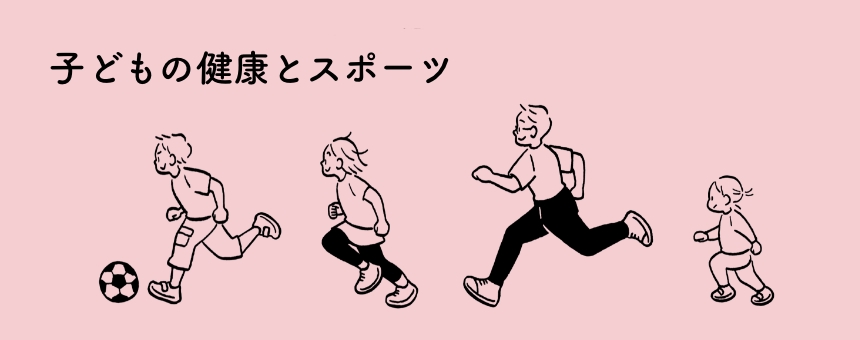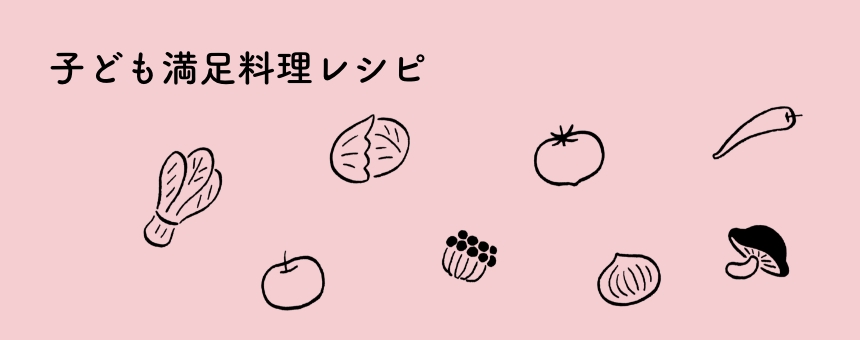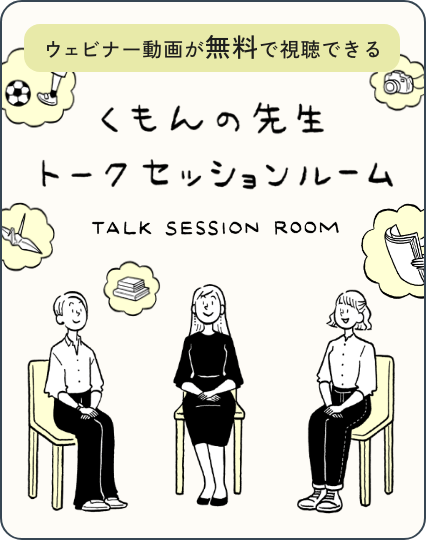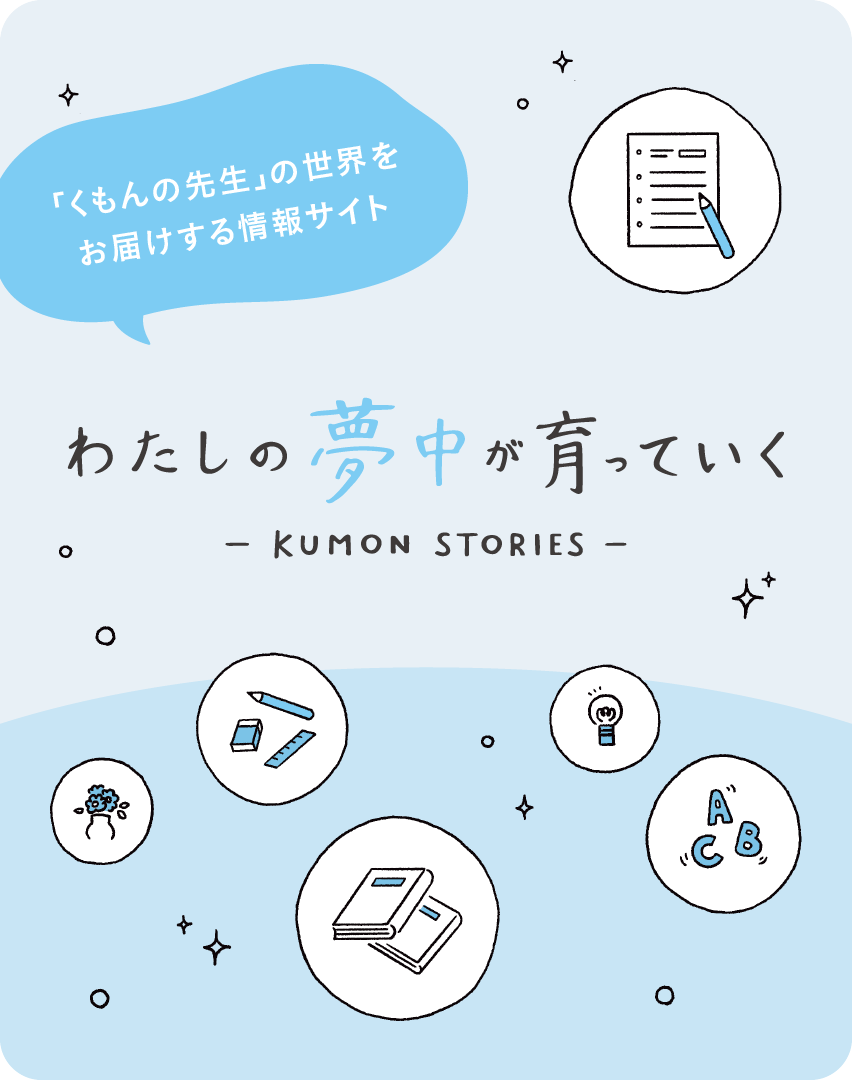「虫歯のない歯にしてあげたい!」と、子どもを持つ親なら誰しも思いますよね。でも、意外と知らないのが歯みがきについての知識。そこで今回は、虫歯になりやすい歯の傾向から、日頃から取り入れやすい予防方法や虫歯予防グッズ、覚えやすい歯みがきの方法などを解説していきます。
乳歯は虫歯になりやすい!?
そもそも、虫歯がなぜできるのかを知っていますか? 虫歯から歯を守るためには、根本的な原因について理解しておくことが予防法にもつながります。
「口の中には一定の虫歯菌がいて、糖質を栄養としています。歯に糖質が残っていると、虫歯菌がエサとして食べた後、酸を発生させ、この酸が歯を溶かしてしまうのです」
と教えてくれたのは、子どもの歯の専門家である、鶴見大学歯学部小児歯科学講座教授の朝田芳信先生。さらに子どもの歯においては、やってしまいがちなとある行動が虫歯の可能性を増やすこともあるそうです。
「子どもの場合、最初から口の中に虫歯菌がいるわけではありません。家族との生活の中で伝播していき、1歳半すぎ~2歳半すぎが一番移りやすい時期。ただし、家族の口の中が健康で、虫歯菌が一定量以下であれば、子どもの口の中に移っても定着しないとされています。
乳歯は、永久歯に比べて歯が少しやわらかいため虫歯になりやすく、口の中の環境が悪くなると、一気に虫歯が広がっていきます。また、2~3歳頃まで哺乳瓶を使っていると、中に入れている飲み物(糖質を含む物)が何であれ、上の歯が虫歯になる“哺乳瓶う蝕(ボトルカリエス)”になりやすいといえるでしょう」
乳歯が生え変わる前の子どもは虫歯になりやすいということを意識して、口内環境や哺乳瓶の扱いに注意しましょう。
子どもが虫歯になりやすい歯とは?

実は、年齢によって虫歯になりやすい歯に傾向が見られるそうです。
「1~2歳前後は、上の前歯です。上の歯は唾液が届きにくいため自浄作用が働きにくく、汚れが溜まりやすいためです。特に、上の前歯の隣接面(歯と歯が隣り合う面)が虫歯になりやすいといえるでしょう。
乳歯が生えそろう2歳後半~3歳は、奥歯の上下です。奥歯の溝には食べカスが残りやすいためです。
4~5歳になると、奥歯の隣接面が虫歯になりやすくなります。
6歳前後~8歳は、口の中の一番奥に6歳臼歯(第一大臼歯)が生え始め、この上下4本が虫歯になりやすくなります。
6歳臼歯の生え始めは歯肉がかぶさっているため、汚れが溜まりやすく、永久歯の中でも最も虫歯になりやすい歯といえます。仕上げみがきをする際は、虫歯になりやすい歯を特に意識してみがくように心がけましょう」
子どもの年齢に応じて虫歯になりやすい歯を意識してみがくことが重要だと語る朝田先生。ここからは、それぞれの歯の特徴や、どのように虫歯から守っていけばいいかについて解説していきます。
奥歯
乳歯、永久歯を問わず、最も虫歯になりやすい歯が奥歯だとされています。特に意識したいのが、奥歯の後ろに生えてくる“第一大臼歯”。6歳臼歯とも呼ばれるこの歯は、最も早く生えてくる永久歯、つまり、一番長く使う歯ということになります。
幼い年齢のうちに生えてくるため、歯ブラシでのケアが行き届かず、食べ物のカスや歯垢が溜まりやすいだけでなく、食べ物をすりつぶす役割があるため、頻繁に使われることで、虫歯になる可能性がさらに高くなるのです。
この6歳臼歯をはじめとした奥歯を虫歯から守るためにできることとして、親が普段から子どもの歯をよく見てあげましょう。“6歳臼歯が生えてきているか”“奥歯までしっかりとみがけているか”を見てあげたり、夜だけでも仕上げみがきをしてあげることも、子どもの虫歯を予防するために大事なことなのです。(*1)
前歯の裏側
前歯の裏側も、歯ブラシが行き届きにくく、虫歯になりやすい場所の一つです。特に下の前歯の裏側は、唾液中のミネラル分が沈着して歯石ができやすく、それが原因で虫歯につながることもあります。(*1)
歯になりやすい理由
奥歯や前歯の裏側が虫歯になりやすい最も大きな原因として、“歯ブラシが当たりにくく、日頃の歯みがきで十分なケアができていない”ことが挙げられます。
歯ブラシが当たりにくい形状をしている
特に奥歯の場合は、その形状が歯ブラシとうまくかみ合わないのです。他の歯に比べて溝やくぼみが多いだけでなく、それぞれが深く細いため、歯ブラシの毛が行き届きにくくなってしまいます。(*2)
歯みがきが上手にできていない
歯ブラシの毛が届きにくいくぼみや溝に食べ物のカスや歯垢が溜まってしまうため、みがき残しが起こりやすく、さらにその歯垢の中にいる細菌が糖分をエネルギー源として利用して酸を生成します。この酸が歯のエナメル質を徐々に溶かして、虫歯が発生するのです。歯垢の除去が不十分で溜まったままになると、虫歯への進行はさらに早くなります。(*2)
子どもの虫歯を予防するには?
年齢による特徴や歯の形状など、子どもの虫歯の原因を見てきましたが、適切な方法での歯みがきや食生活の改善など、予防としてできることをあらためて考えてみましょう。
まずは歯みがきに興味を持たせることが大切
一日に少なくとも2回、適切な方法での歯みがきを行うことによる日々の十分なケアが、子どもの歯を虫歯から予防する最大の手段になります。そのためにまずは、子どもが歯みがきに興味を持ち、歯科医師や歯科衛生士に正しいブラッシング法を教わったり、フロスや歯間ブラシといったケア用品の使用を覚えていけるよう、親としてもサポートをしていきましょう。(*2)
シーラントやフッ素塗布
歯にコーティングをすることで、溝を塞いで食べ物の残りカスの蓄積や細菌の侵入を防ぐシーラントや、エナメル質を強化し、酸によって歯が溶けるのを防いで虫歯を予防するフッ素を用いることも虫歯予防に適しています。なかでもフッ素なら、歯磨き粉や洗口液に含まれているものも多いので、日々のケアに手軽に取り入れることができます。(*2)
食生活を見直す
ぜひ、食生活の改善も視野に入れてみてください。前述のとおり、口内の細菌が虫歯の原因となる酸を生み出す際のエサとなっているのが糖質。そのためスナック菓子や甘い飲み物を控えるなど、糖質の摂取を意識的に制限してみるのも効果的です。また、ビタミンやミネラルを豊富に含むバランスのとれた食事を心がけることで、歯と歯茎の健康を支えることができます。(*2)
定期的な歯科検診を受ける
少なくとも年に1回は、歯の専門家である歯科医師による診療を受けるようにしましょう。初期の虫歯やその他の口内の問題を早期に発見し、治療することができます。
これらの習慣を日常生活に組み込むことで、虫歯のリスクを大幅に減らし、長期的な口内健康を維持することが可能です。(*2)
1~2歳は、歯みがきに興味を持たせること
子どもの虫歯を予防するには、まずは歯みがき習慣を身につけさせることが大事だと朝田先生は言います。
「とはいえ、焦らず、年齢に応じて、ステップバイステップで進めていくことが大事です。
1~2歳の間は、歯みがきに興味を持たせることが大切。まだ、何のために歯みがきをするかを理解できていないので、とにかく歯ブラシを自分で持ち、口の中に持っていき、動かせたらそれでいいのです。最初は、前歯に歯ブラシを当てるのも難しいので、歯みがきをしているような雰囲気でかまいません。
1歳6カ月頃になると、奥歯が生えてくるので、『奥歯が生えてきたよ』など、歯の変化を教えてあげながら、奥歯の溝をみがく意識を持つように促してあげましょう。
2~3歳は、運動機能が発達してくるので、歯ブラシを動かすのが上手になってきますが、まだ自由にみがかせて『歯ブラシを当てるのが上手になってきたね』など、よいところをほめてあげましょう。
3歳を過ぎると、乳歯が生えそろうので、ブラッシングを意識させながら、習慣づけることが大事です。親御さんと洗面所で歯みがきをしたり、兄弟がいれば一緒に行うのもいいでしょう」
簡単で覚えやすい歯みがきの仕方「9分割法」

3歳を過ぎて自分で歯をみがける年代になってきた子どもに向けて、覚えやすい歯みがきの方法“9分割法”や、みがく際のポイントを朝田先生が教えてくれました。
利き腕の方から、歯を9分割に分けてみがいていきます。
右利きの場合、まず、口を大きく開けたアーッの状態で、
①右側上の歯の溝
②右下の溝
③左側上の溝
④左下の溝
をみがきます。これで4カ所終了です。続いて、口を閉じてイーッと噛み合わせた状態で、
⑤右奥の表側
⑥左奥の表側
⑦前歯の表側
の3カ所をみがきます。最後に、口を開けて
⑧上の歯の裏側
⑨下の歯の裏側
をみがきます。


「9分割の1カ所をみがく時間は、約20秒を目安にするといいでしょう。
また、親御さんが、みがく場所に合わせて『いち(右上溝)、に(右下溝)、さん(左上溝)、しー(左下溝)、ごー(右奥表側)、ろく(左奥表側)、なな(前歯表側)、はち(上の前歯裏側)、く(下の前歯裏側)』と声をかけてあげると、子どももすぐに覚えられ、歯みがきが難しいものではないという意識を持つようになるものです。なお、この時期は、まだ汚れを落とすのは二の次です。歯みがきの習慣をつけさせることが重要です」
5歳を過ぎたら、肩とひじを固定してブラッシング
5歳を過ぎたら、歯みがきのスキルアップを目指せると朝田先生。
「肩とひじを固定してブラッシングできるようになったら、技術的に高くなっている証です。
また、歯みがきのスキルが身についてきたら、一度、歯医者さんに行って、歯科衛生士さんからブラッシング方法を習うといいでしょう。歯ブラシを小刻みに横に動かして1~2本の歯をみがくスクラビング法を教えてくれるはずです。
子どもがきちんと歯をみがけているかどうかをチェックするために、時々、染だし液(歯垢染色液)を使うことをおすすめします。赤く染まった箇所がみがけていない部分なので、子どもも『ここをみがかなければ!』と意識するようになるでしょう」
まとめ
いかがでしたか? 前編では、虫歯になりやすい歯や日頃からできる予防、さらに覚えやすい歯みがきの方法「9分割法」をお届けしました。後編では、歯ブラシの選び方や仕上げみがきの卒業時期についてご紹介します。
(*1)茨木クローバー歯科:どの歯が一番虫歯になりやすい?どうやって虫歯から守ればいい?(2025年1月6日閲覧)
(*2)クローバー歯科クリニック:虫歯が出来やすい場所とその理由とは?(2025年1月15日閲覧)
この連載の他の記事はこちら
取材・文:サカママ編集部 取材協力:朝田芳信(鶴見大学歯学部小児歯科学講座教授) 参考文献:朝田芳信著『ドクター朝田の 間違いだらけの子どもの歯みがき』(春陽堂書店)