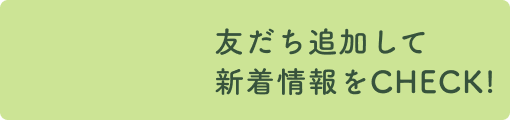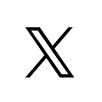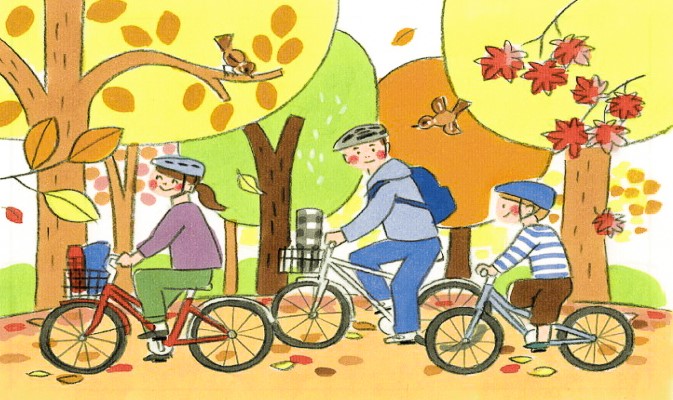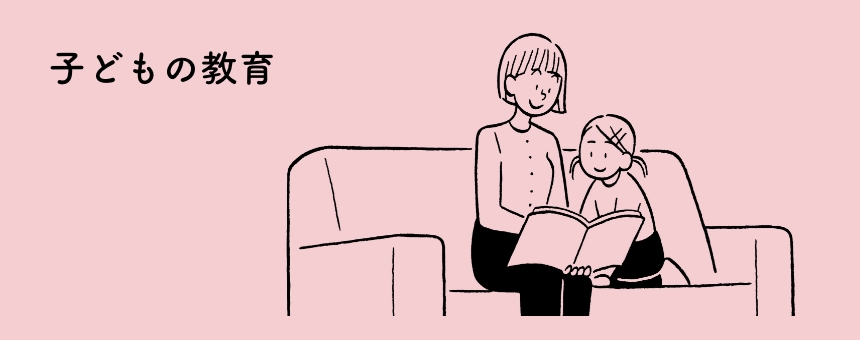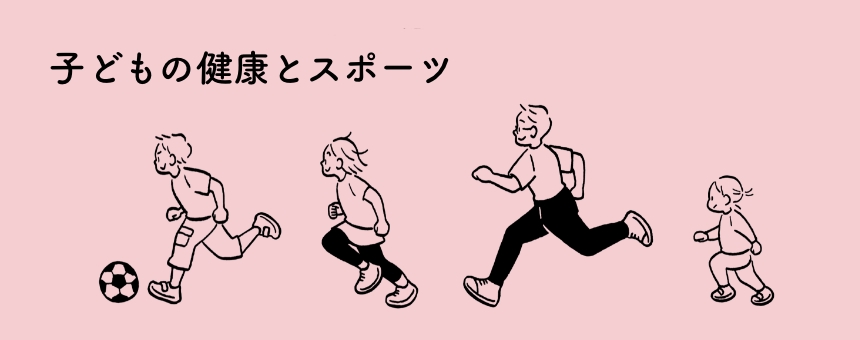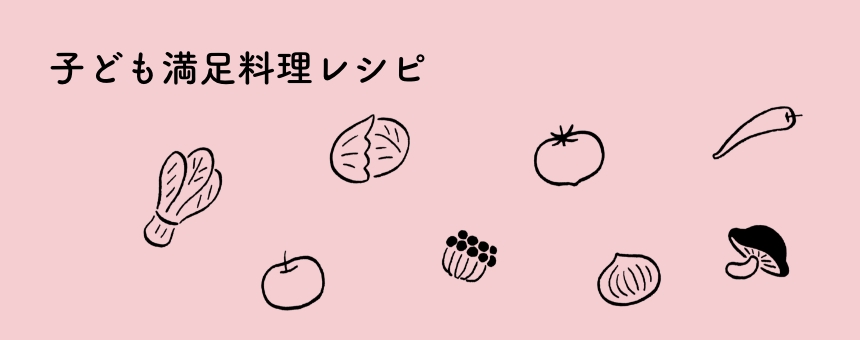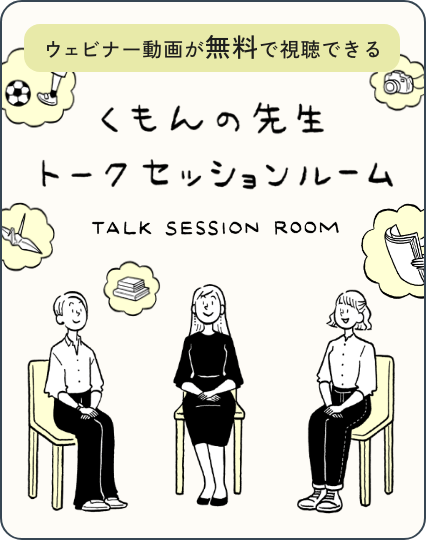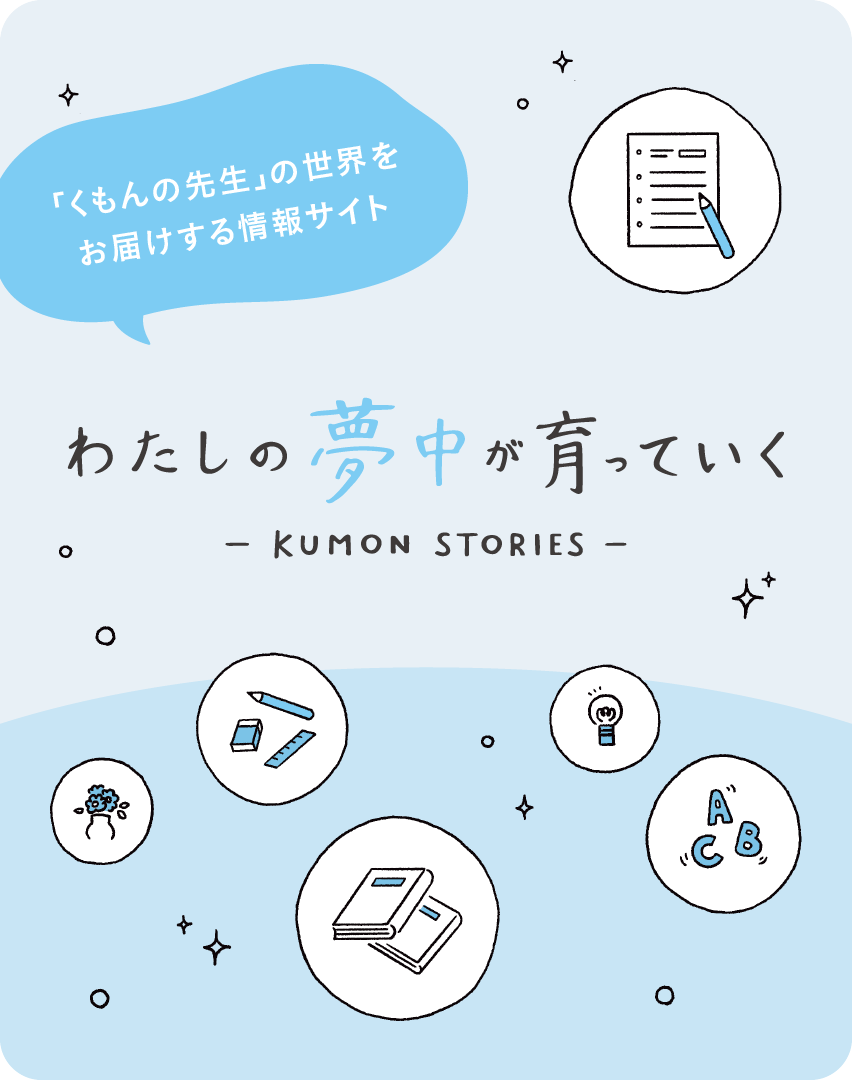最近、足の指が使えない子どもが増えていると言われています。足の指が上手く使えないと、足裏の筋肉に影響するだけでなく、脳の成長にも関係するとか!後編では、子どもの足を育てる秘訣をお届けします。
足の指が使えない子どもが増加!

昔は外遊びをする機会も多く、その遊びの中で足が自然に鍛えられていたもの。でも今の子どもたちは公園で遊ぶことも少なくなり、足を育てる環境が減ってきています。さらに、フローリングの室内など、足にダメージを受けやすい生活環境でもあるのです。
そのため、今、子どもたちに対して「足育(そくいく)」が注目を集めています。「足育」とは、靴の選び方や履き方、足の運動やケアなど正しい知識を持って、足の機能を育てるということです。
とくに昨今、足の機能の中でも、足の指が使えない子どもが増えています。足の指が上手く使えないと、足裏の筋肉の発達に影響するだけでなく、実は脳の成長にも関係すると言われているのです。
足の指をしっかり使うことができると、ふくらはぎに刺激が入り、血液を押し戻す作用が上手く働くものです。つまり、血液の流れがよくなるのです。
しかし、足の指を使うことができないと、血流が悪くなることに繋がります。すると、脳の血流も悪くなることから、結果、脳は活性化しにくいのです。
また、血流が悪いと疲れが溜まりやすく、集中力も持続しないことから、学力に影響を及ぼすことも考えられます。
「足脳育(そくのういく)」という言葉もあり、足の機能を育てることは、脳の成長のためにも重要というわけです。
子どもの足は、半年で約0.5㎝のペースで成長

子どもの足の成長は、1歳から2歳半までは半年で約1㎝、それ以降、成長期を終えるまでは、半年で約0.5㎝のペースで大きくなると言われています。子どもは、靴のサイズが合わなくなっても、黙って履き続けていたり、我慢して足指を丸めて履いていることもあります。すると、足の指を動かせなくなるだけでなく、扁平足の悪化や骨の変形など、足のトラブルを招いてしまうことにもなるのです。
靴の中で足の指が動かせる状態を保つためにも、親が子どもの足と靴のサイズが合っているかを定期的にチェックしましょう。一番の理想は、2週間に一度チェックすること。それが難しい場合は、1か月に1度、最低でも3か月に一度は、親の責任だと思って確認しましょう。
また、足に合った靴を選ぶことも大事です(前編参照)。
5本の足指を意識して歩くことが大切

日常生活の中では、5本の足指をしっかり意識して歩くことが重要です。というのも、最近は、「浮き指」の子も増えているからです。浮き指とは、立っているとき、歩いているときに、足の指が浮いて地面に接していない状態、または接していても足の指先に力を入れて踏ん張れない状態のことです。
足指の中で、親指は使えても、小指を上手く使えない子は多く、活発な子でさえも、小指が浮いていることがあるのです。
しかし小指は、5本の足指の中でもとくに重要。それが、よくわかるのが下記のバランステストです。親子でやってみるといいでしょう。

[バランステスト]
1.子どもは立った状態で、体の後ろで両手の指を組む。
2.大人は、こぶしをにぎって、子どもの手の上にのせ、体重をかける。
*子どもは倒れないように踏ん張って!
体が倒れなければ、体の後ろ側のバランスが、しっかりとれている証です。
次に、2のときに、子どもは足の小指に力を入れてみてください。すると、最初は倒れてしまった子も、小指に力を入れるとバランスは崩れずキープできるはずです。
このテストからもわかるように、体の後ろ側のバランスをとるのに、小指は大いに関係しています。そのため、小指が使えないと、体の後ろ側のバランスがとりにくくなり、その結果、膝や腰など他の関節でバランスをとろうとするので、股関節や膝、腰などの痛みを招くことにもなってしまいます。
なお、体の前側のバランスをとっているのが親指です。上記のテストの1の時に、体の前で両手を組んで、バランステストを行ってみてください。親指に力を入れて踏ん張ると、前に倒れずにキープできるはずです。
よくケガをするという子は、もしかしたら5本の足の指が使えていないのかもしれません。歩くときに、小指を接地させることを意識させるだけでも、変わってくるはずです。
とはいえ、子どもは、どうしてもベタベタと歩いてしまいがち。足指を鍛えるためには、日頃から足指じゃんけんや足指でビー玉をつかむなど、足の指を刺激させる運動を取り入れるといいでしょう。
取材・文:サカママ編集部 取材協力:那須友和(NASYU株式会社代表取締役。医療とスポーツの現場でインソールの研究開発をし、インソールマイスター資格を作り、治療家やトレーナーを対象に、全国で足の予防医療の普及活動に務める。またインソールメーカーとして、初の経済産業省支援企業に認定され、全国のサッカーチームで足の教育講演も実施)