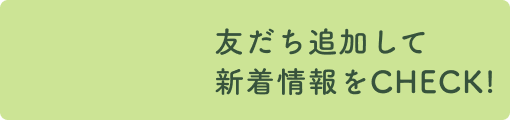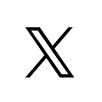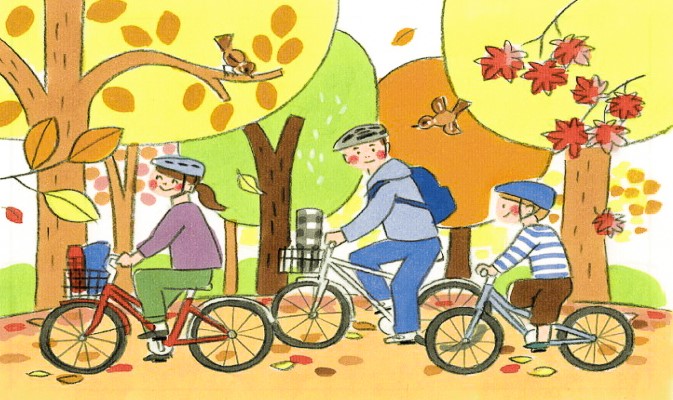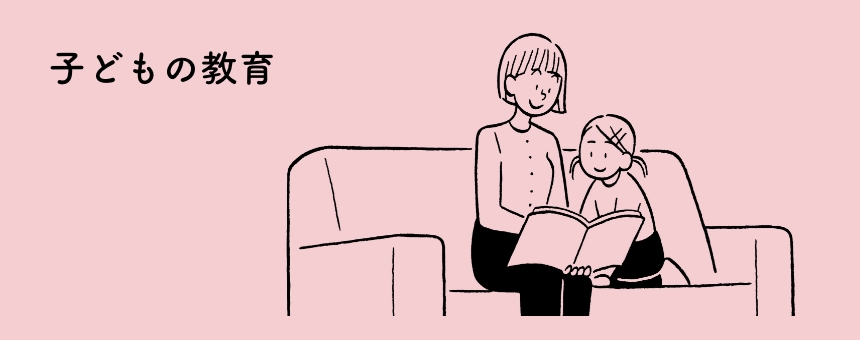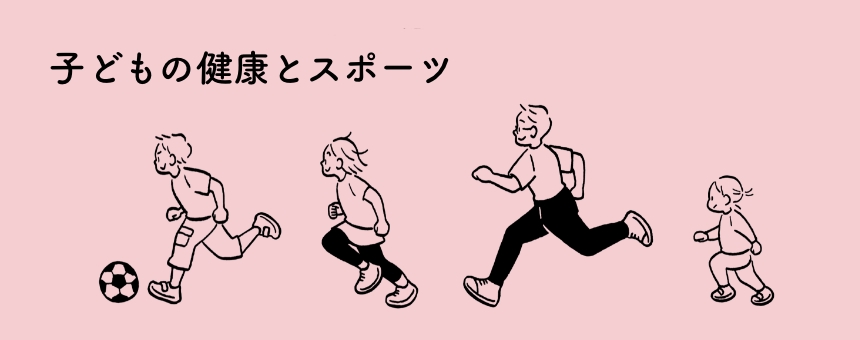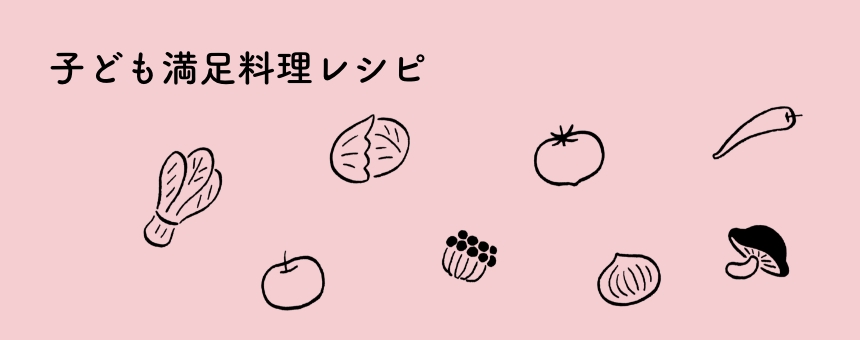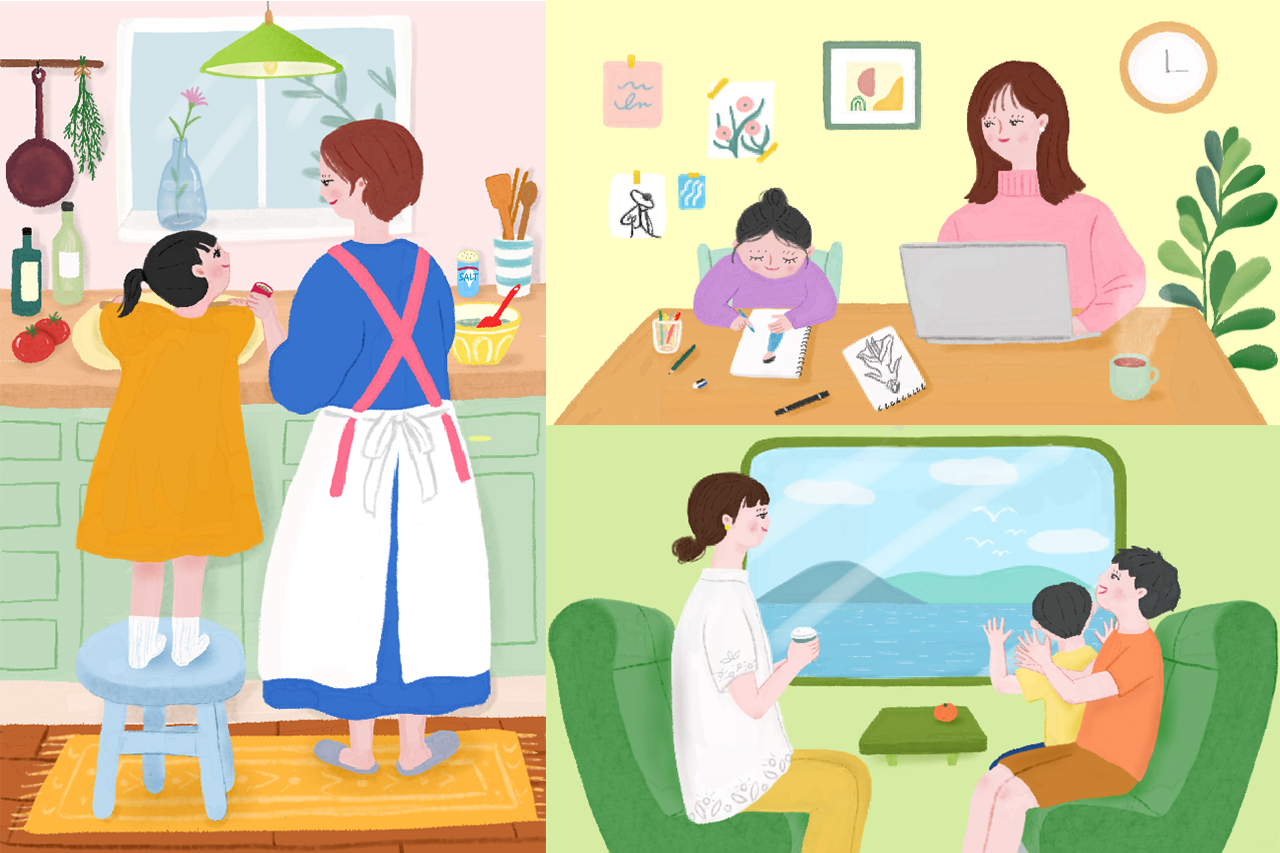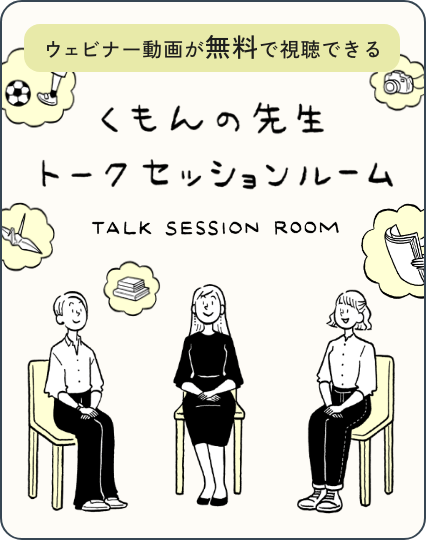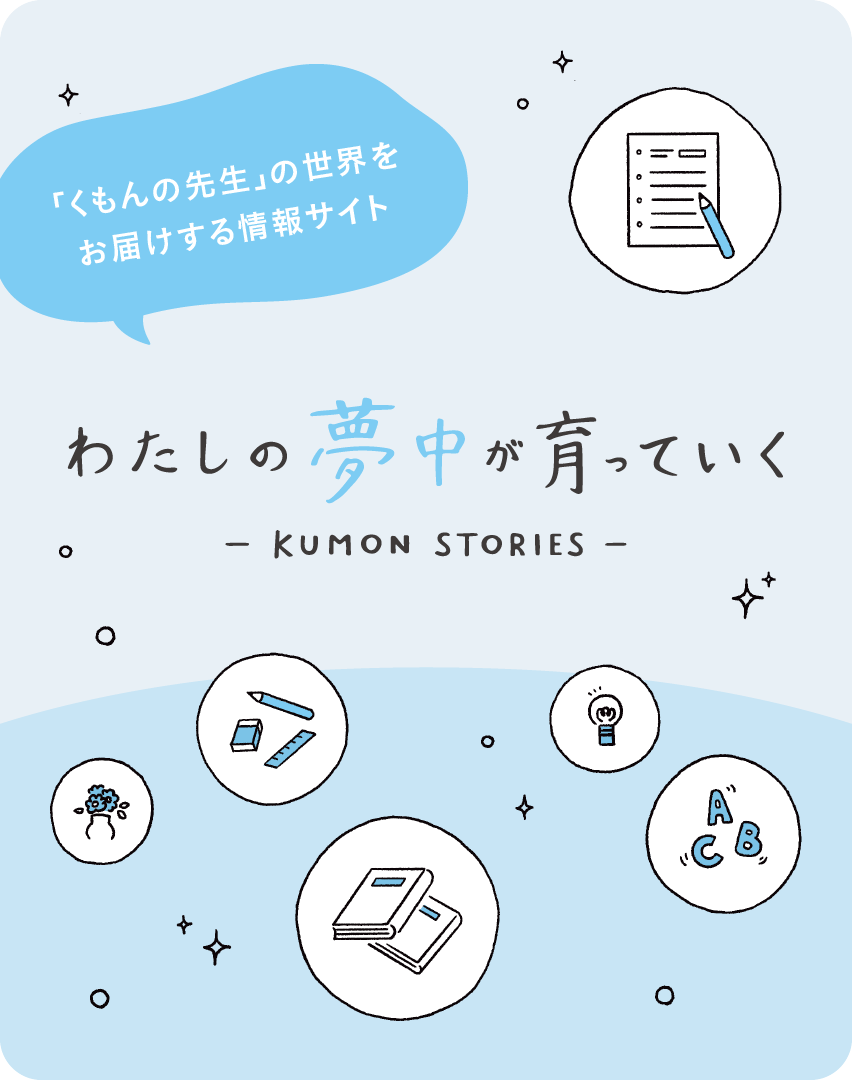子どもが朝起きられない…と悩んでいる保護者もいるのではないでしょうか。睡眠の質を低下させてしまう要因の一つが、睡眠にまつわる病気です。そこで知っておきたい睡眠障害や対処法を、睡眠・精神科専門医である上島医院院長の渥美正彦先生にお聞きしました。
<教えてくれた人>
渥美正彦さん

大阪市立大学医学部卒業。大阪警察病院(神経科)、国立病院機構やまと精神医療センター(精神科)、馬場記念病院(脳神経内科)、近畿大学医学部付属病院(脳神経内科)を経て、2004年6月から上島医院に入職。05年6月より同医院併設南大阪睡眠医療センター長、10年4月より同医院院長。日本では数少ない睡眠専門医であると同時に、チャンネル登録者12万人を超える人気医療系YouTuber。
休日にたくさん寝ていたら、睡眠不足症候群かも!?

子どもの睡眠時間、しっかり確保できていますか?
1日30分の寝不足でも、それが長期間続くとダメージが蓄積し、朝起きられない、だるい、やる気が出ない、怒りっぽくなる、学習機能が落ちる、風邪にかかりやすくなるといった様々な悪影響が出てきます。
睡眠不足は、正式には「睡眠不足症候群」と呼ばれる睡眠障害(睡眠に関連した多種多様な病気の総称)の一種。睡眠不足症候群だと自覚していない人が多いというのも特徴です。
休日になると、昼近くまで寝ているという子もいるのではないでしょうか。いつもより2時間以上以上多く寝ている場合は、睡眠不足症候群かもしれません。
睡眠不足症候群を治すには、まずは寝ること。日本では12〜13時間の睡眠を4日間とると、5日目から回復が見られたという研究結果がありますが、子どもはそれだけでは足りない可能性も。深刻な状態になる前に、日頃から睡眠時間を十分とるようにしましょう。
いびきは危険信号!子どもに多い睡眠の病気とは?

子どもがいびきをかいていることはありませんか?いびきは睡眠障害のわかりやすいサインです。
大人は健康な人でもいびきをかくことがありますが、子どもは口呼吸に対する抵抗性が弱く、鼻がつまっているだけで呼吸が止まりやすい状態になります。もしいびきをかいていたら、絶対に放置せず対処しましょう。
応急措置としては、鼻水や異物をとり除いて鼻の通りをよくしてあげること。症状がひどい場合は「睡眠時無呼吸症候群」の可能性も考えられるので、医療機関に相談するようにしましょう。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が止まる病気で、日中の眠気や集中力の欠如を引き起こします。
最も多い原因は鼻づまり。子どもが毎晩のようにいびきをかいて苦しそうにしている場合は、アデノイド(鼻の奥にあるリンパ組織)と扁桃腺が肥大し、鼻の奥を塞いでしまっている可能性があります。両方とも手術で切除できるので、耳鼻咽喉科を受診しましょう。
この他にも、子どもの主な睡眠障害としては「むずむず脚症候群」や「過眠症」が挙げられます。
むずむず脚症候群
布団で安静にしているのに脚を動かしたくなり、むずむずするような不快感に悩まされる睡眠障害です。子どもが夕方から深夜の時間帯に落ち着きがなくなり、多動になるという場合は、むずむず脚症候群の可能性があるでしょう。
発症する人の多くは、鉄不足が原因。薬や食事で鉄を補うことによって、治ることも。ただし、発達障害や、睡眠時無呼吸症候群の眠気による多動といったケースなど、別の原因が隠れていることもあるので、医療機関への受診をおすすめします。
過眠症
十分な睡眠をとっているにもかかわらず、日中に眠くなってしまう睡眠障害です。
10代前半で発症することが多く、発作のように居眠りをしてしまう「ナルコレプシータイプ1」の他、「特発性過眠症」や「反復性過眠症」などもあります。
子どもが朝起きられない原因は?
子どもが朝起きられないと悩んでいる保護者もいるのではないでしょうか。朝寝坊が続くと、「起立性調節障害」など自律神経の病気を疑いがちですが、睡眠にまつわる病気が一因であることも。夜に眠くならず午前中いっぱい寝ているといったケースが頻繁に見られるのなら、体内時計のリズムが乱れる「睡眠・覚醒相後退障害」の可能性もあるでしょう。
ただ、10代前半くらいで朝寝坊になるのは、生理的には異常なことではないのです。
人間は第二次性徴期に入ると夜型になるもの。第二次性徴期は一般的に、女子が10歳~15歳前後、男子は11歳6か月~16歳前後で、この頃から夜型へと進行し、女子は20歳、男子は21歳を過ぎたあたりで朝型の傾向へと変わっていきます。少しの寝坊であれば、正常な範囲内とも言えるでしょう。
子どもの「朝起きられない」の対処法

学校に行く時間に起きられない、夜遅くまで眠れないという子は、起床後すぐに朝日を浴びるようにするといいでしょう。屋外で30分程度の散歩ができればベストですが、毎朝「お天気チェック」をするだけでも最初は十分。窓を開けて天気を確認できるくらい光を浴びれば、体内時計に朝を伝えるメッセージになります。また、体内時計のリセット効果を高めるためにも、朝ごはんを食べるようにしましょう。
夕方以降はカフェインを控えることも大事。とくに気をつけてほしいのが、エナジードリンクです。カフェインが多く含まれ、依存性があり、循環器系に対する悪影響も。コーラ飲料などもなるべく控えるようにしましょう。
前編で紹介したように、夜は照明を調節し、寝る前のスマホは目との距離に注意することも大切です。
睡眠習慣を見直すためには睡眠記録をつけるのもいいでしょう。手書きが大変であれば、スマートフォンを使ってもOK。ゲームと紐づけると子どもでも継続しやすいので、ゲーム性のあるスマホアプリの活用もおすすめです。遊びの延長で早起きができるようになる可能性も。
子どもだけでなく保護者も睡眠の見直しを!
睡眠障害のような症状でなくても、朝起きられない、眠れない、強い眠気に悩まされているなど、子どもの睡眠で困っているならば、睡眠の専門医に相談するのも一つの方法です。日常生活の中で何がうまくいっていないのかは、自分や家族では意外と気づかないもの。専門医に相談してみると、問題解決の答えやヒントが見つかるはずです。
子どもの睡眠は、保護者の睡眠の縮図です。夜になっても明るい室内でいくら子どもに「早く寝なさい」と言っても、質のよい眠りにはつながりません。保護者が5、6時間の睡眠で済ませていたら、悪い見本になってしまうことも。子どもの睡眠について考えるとき、まずは保護者自身が睡眠習慣や家庭の生活環境を見直してみるといいでしょう。