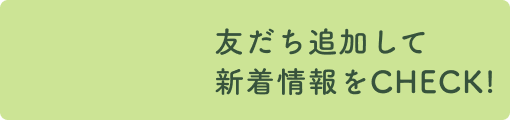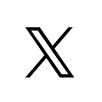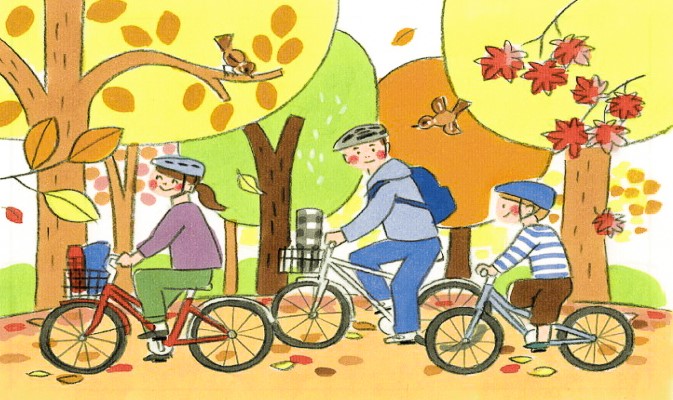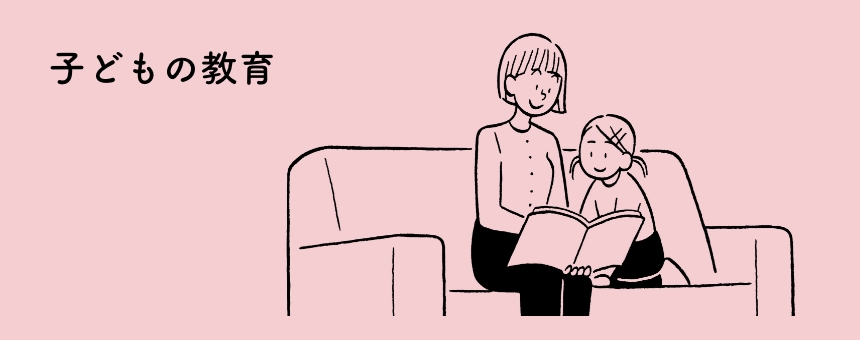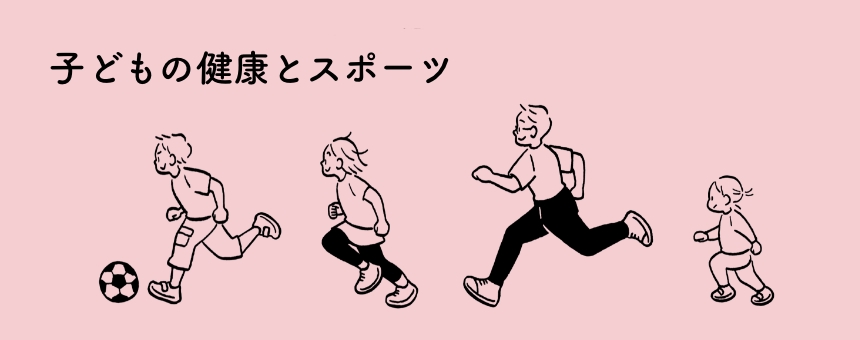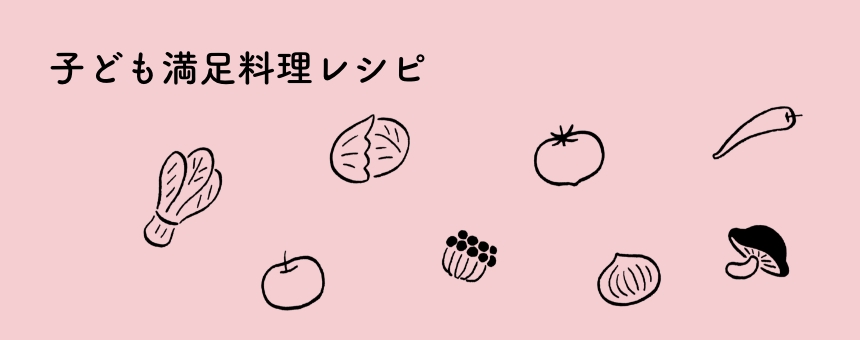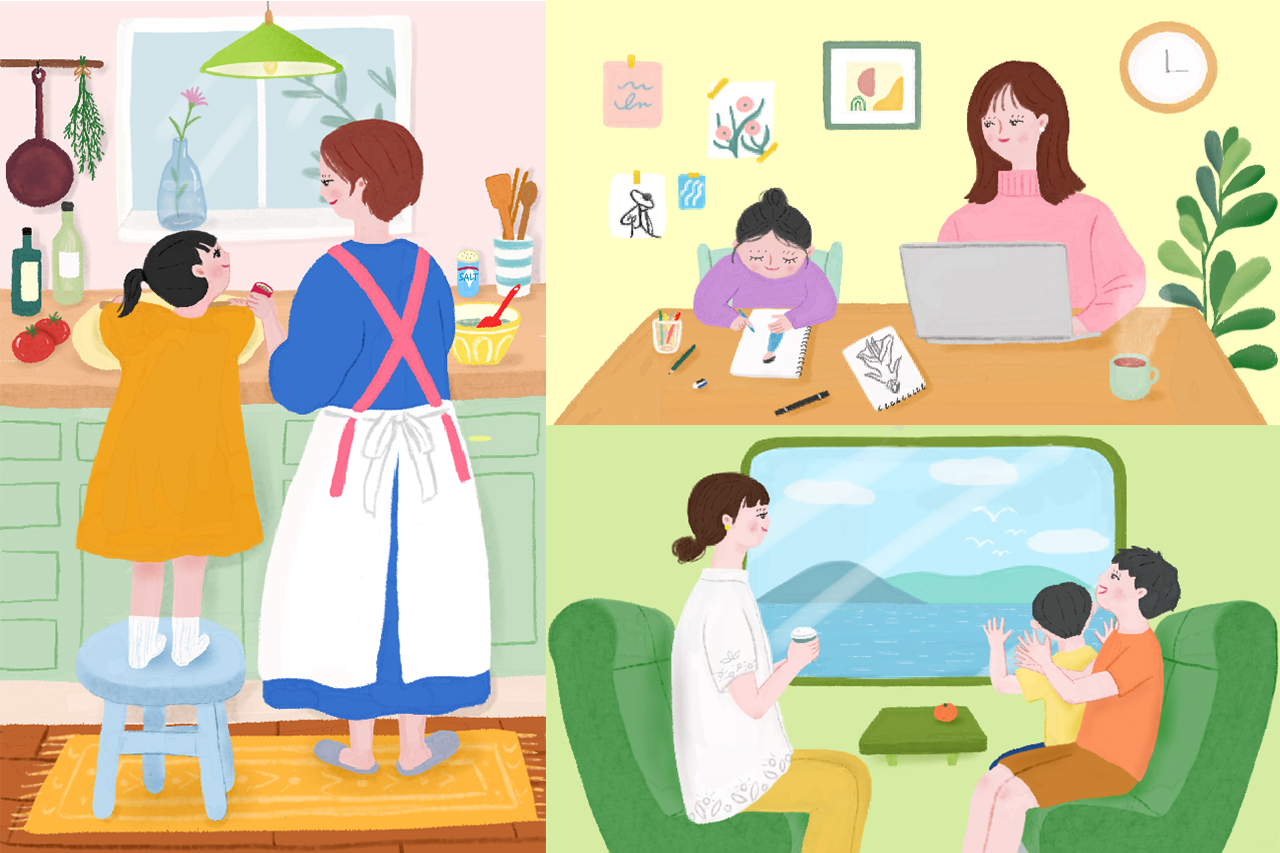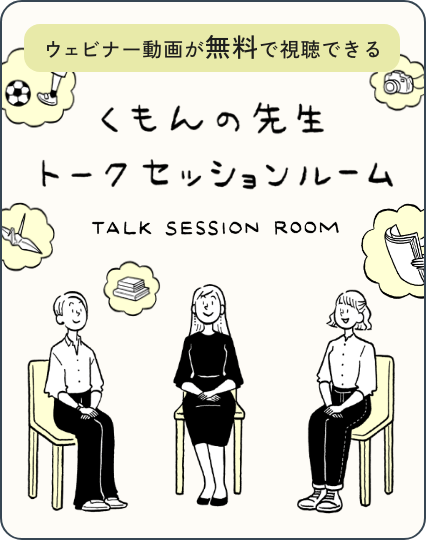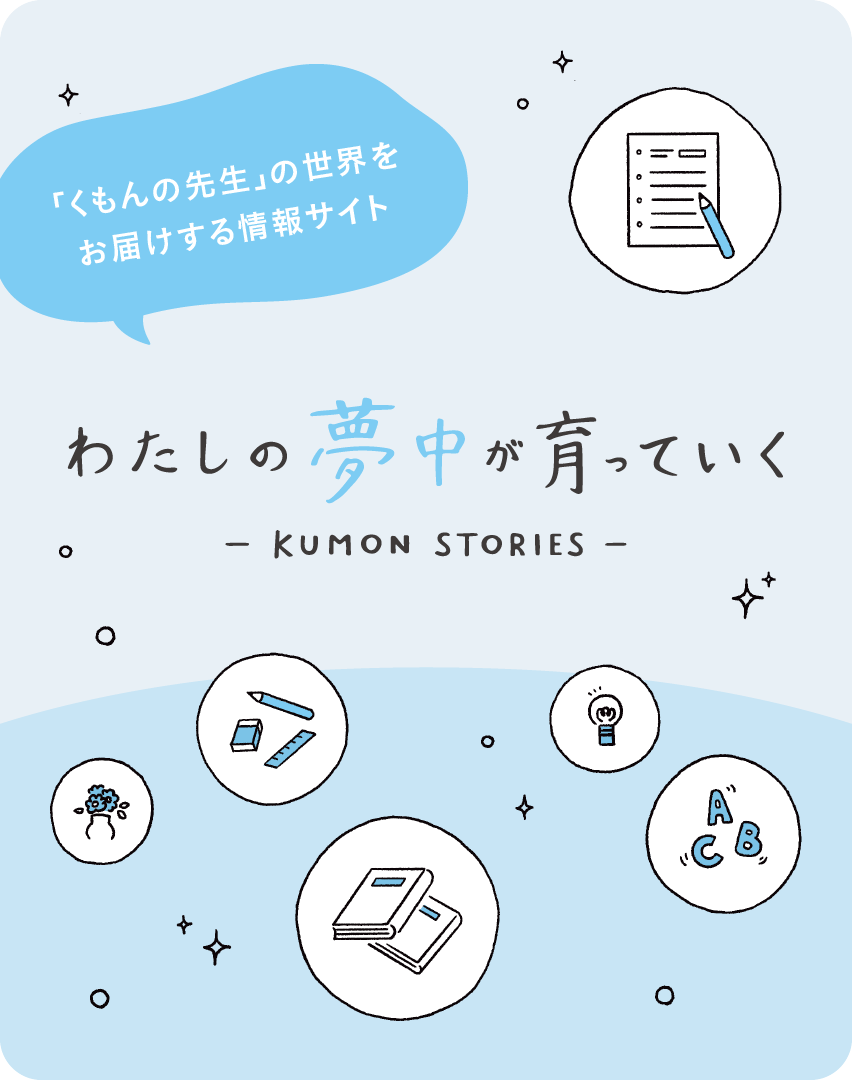「小学校入学準備、いったい何から始めたらいい?」そんな不安の声に応えるため、自身も中学3年生の長女と小学3年生の長男を育てる母であり、愛知県でくもんの教室を運営する今井有紀先生にお話をお聞きました。今井先生の子育て経験とくもんの先生としての経験をもとに、入学前に“やっておいてよかった!”と感じた入学準備を、「学習面」と「生活面」の両方からお話しいただきました。くもんの先生の視点から、無理なく楽しく始められる入学前準備のヒントをお届けします 。
<教えてくれた人>

今井 有紀先生(愛知県)
中学3年生、小学3年生の2児の母。「自分の好きや得意を生かした仕事がしたい」と、くもんの先生に。「18歳になったときに自分の頭で考え自立して学び、自分の人生を歩める人を育てたい」という想いで教室運営をしている。
「私は“入学準備”というより『子どもたちが生活で困らないようにしてあげたい』という気持ちで教室の保護者の方にお話ししています。特に、ひらがなや数字は、日々の暮らしの中で必要なもの。だからこそ、できるだけ早いうちから、楽しみながら身につけてもらえたらいいなと思っています」(今井先生)
【学習面】
自分から楽しく本が読めるきっかけをつくる
小学校に入学して最初に教室へ行ったとき、黒板に「にゅうがく おめでとう」と書かれていても、もしひらがなが読めなかったら、少し寂しい気持ちになるかもしれない、というのが今井先生のお考えです。実際に、自分の名前が読めずに席の場所がわからないというお子さんの話もよく耳にするそうです。そのため、入学前にひらがなが読めるようになっていると、子ども自身の安心感につながるのだとか。
また、ひらがなを覚えたり語彙を増やしたりするのにおすすめなのが「本を読むこと」だそうです。今井先生ご自身も、お子さんが赤ちゃんの頃から絵本の読み聞かせの時間を大切にしてきたそうで、「早くから本に親しむことは、子どもにとって良いことばかりだと感じています」と話します。

「私も夫も本が好きだったこともあり、読み聞かせをするなかで『この本、好きそう!』という反応を私たち大人も楽しんでいました。すると自然に、子どもたちは待ち時間などにも自分から本を楽しむように。ただ大切なのは、“無理に読ませないこと”。一緒に読んだり、遊びの延長で楽しんで読んだりすることで、“読まされている”感がなくなり、自然と読む習慣がついていくと思います」(今井先生)
さらに語彙を増やす方法として、今井先生のご家庭では、しりとりもよく取り入れていたそうです。
「しりとりは、楽しみながら語彙を増やすのにぴったりな遊びです。『今はこのくらいの言葉がわかるのね』と子どもの語彙や言葉への理解度が分かることで、親としてこれからどう関わればいいかのヒントにもなりますよ」(今井先生)
【学習面】
えんぴつで紙に絵やひらがなを書くのを楽しむ
昨今、タブレット学習が増えていく中で、いざ鉛筆を持って紙に書こうとすると、筆圧が弱くてうまく書けなかったり、時間がかかったりして、戸惑う子を多くみるようになりました、と今井先生。
「小学校でもタブレット学習はありますが、私の地域では1年生の3学期ごろから使用されることが多く、それまではプリントやノート中心の学習です。だからこそ、鉛筆や紙に少しでも慣れておくことが、入学後のスムーズなスタートにつながると思います。実際、消して書き直すだけで思いのほか時間がかかってしまうことも多いんです。なので、” 紙に鉛筆で書くことに慣れる”ことで、学校での授業がもっと楽しくなると思うんです」(今井先生)
とはいえ、無理に練習をさせなくても大丈夫。家族やお友だちにお手紙を書いたり、お絵かきを楽しんだり、書くことを遊びの一つとして取り入れるだけで十分です。

「例えば『○○ちゃんにお手紙書いてみよう!』と声をかけるだけでも、自然と書くことに親しめると思います。そんなふれあいの時間が、親子にとって楽しいひとときになれば嬉しいですよね」(今井先生)
【学習面】
数字に慣れ親しんでおく
数字については、勉強として教えるのではなく、駐車場の番号やエレベーターの階数、家族やお友だちの誕生日など、身近な場面で使う・話す・見つけることを通して、楽しく覚えることができるそうです。また、数字は「1〜10まで書けた!」という達成感も得やすく、好きになるきっかけが作りやすいのもポイントだと今井先生。
「一緒にカレンダーを見ながら、『今日は何日かな?パパのお誕生日は17日だよね』と指差して声をかけるだけでも、自然と数字に親しむ時間になります」(今井先生)

今井先生は、「120まで親しんでおけると、さらに安心です」と話します。
「120まで理解していると、数字が上がっていく仕組みを自然と予想ができるんです。実際、119の次が200になってしまうことは、小さい子の場合はよくあります。120までの数の並びに親しんでおくと、学びの土台作りにとても役立ちますよ。もちろん、無理に覚えさせる必要はありません。『120まで数えてみよう』とゲーム感覚で楽しんだり、数字のポスターで指さしゲームをしたりするだけでも、楽しい覚え方になりますよ」(今井先生)
【生活面】
時間の感覚を知り、時計に親しむ
時計の読み方は、小学1年生で本格的に学び始め、2・3年生では時間の計算へと進みます。でも実は「時計が苦手」「読めない」という子も少なくないそうです。
「教室に来てくださる保護者の方には、『時計は生活に必要なことだから、お勉強ではないんですよ』とお伝えしています。たとえば『おやつは3時だよ』『朝ごはんは7時からだからあと10分だね』のように、お子さんが喜ぶような身近な出来事と結びつけながら、日常の中で少しずつ教えていくといいと思います」(今井先生)

また、今はデジタル表示の時計が主流ですが、アナログ時計にも慣れておくことが大切だといいます。針が動くアナログ時計を知らない場合もあるので、家庭で触れる機会をつくっておくと、学校でも戸惑わずにすむそう。100円ショップなどで売っている針を動かせるアナログ時計を使い、「3時にしてみよう」と針を合わせる練習をするのもおすすめとのことです。
【生活面】
自分でやってみる力を育てる
小学校は、これまでの幼稚園や保育園とは環境が大きく変わります。着替えや持ち物の用意など、自分のことは自分でできて、自分の気持ちを言葉で伝える力があれば、安心して学校生活を送ることができるのではないでしょうか。
「普段から家庭でも『今日は何をしたの?』『誰と遊んだ?』といった会話をすることで、”誰が・何を・どうした”ということを自分の言葉で伝える練習ができます。『スプーンを取ってきてくれる?』といった簡単なお手伝いを頼んでみることでも十分です。家庭でも”人の言葉を聞いて自分で考えて動けるかどうか”ということを意識しておくことで、小学校で困る場面が減らせるのではないでしょうか」(今井先生)

また、今井先生の教室では、入会時から「自分の学習の準備や身の回りのことは自分でできるように」と、少しずつできることを増やしていく指導を行っているそうです。合わせて、“集中して考え、短い時間で正確に解答する習慣”が身につくよう、日々の声かけも意識されているとのこと。
「小学校では、自立した行動が求められる場面が増えます。自分のことが自分でできると、お子さん自身も保護者の方も楽になると思うんです。なんでもやってあげるのではなく、『自分でやってみたい!』と前向きな気持ちのうちに、たくさんの経験を積ませてあげてください。その積み重ねが、お子さんの“自分でできる!”の自信につながると思います」(今井先生)
「楽しそう!」が学びのきっかけになる
今井先生の元には、保護者の方から入学前の不安や悩みなど多くの相談が寄せられるそうです。4月のスケジュールや学習の進み方、保護者が学校に行く頻度など、入学してからの生活がイメージしやすいようなお話をすることも。保護者の方の声に真摯に寄り添いながら、教室での指導や面談を通して一人ひとりの成長を見守り、「毎日元気に楽しく学校に行ってね」と毎年子どもたちの背中を押して送り出していると話します。
「教室に来てくださる就学前のお子さんを持つ方には、『大変ですが、入学前からほんの少し意識しておけば、入学後の小学校生活を楽しく過ごせますよ』とお伝えしています。私は勉強だけでなく、お友だちと遊ぶことやいろいろな体験も大切にしてほしいと思っています。そのために、教室では子どもたちが自然と自信をつけていけるようなサポートを心がけています。勉強はどうしても”やらなければならないこと”になりがちです。まずは『楽しそう!やってみたいな』と自然に思えるきっかけづくりが、学びの第一歩。だからこそ、無理なくスタートして苦手なものにしないことが何より大切なことだと思っています」(今井先生)