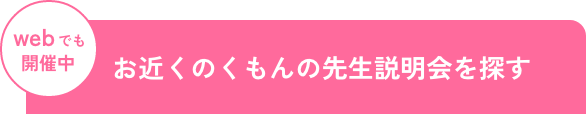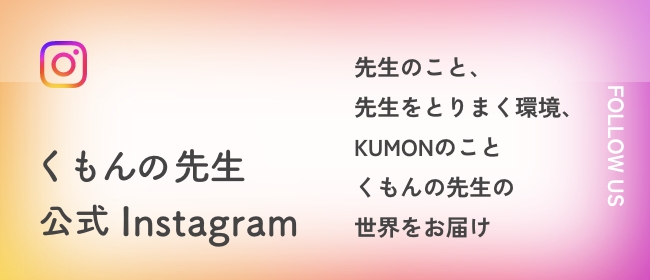KUMONは、全国各地の公文式教室の運営にとどまらず、児童養護施設や特別支援学校、自立訓練校などでの学習支援を行っています。「学習者一人ひとりの可能性を信じ、その能力をさらに引き出したい」というKUMONの想いと実践は、施設・学校・企業の現場にまで広がっています。今回は、実際に公文式を導入いただいている3つの施設の事例を通して、導入のきっかけや導入後の変化をご紹介します。
児童養護施設「日本水上学園」の取り組み

児童養護施設は、さまざまな事情により親や保護者と暮らすことができない子どもたちが生活する施設です。2025年7月現在、全国80以上の施設で公文式が導入されており、神奈川県横浜市にある「日本水上学園」もその一つです。同学園では、施設で暮らす小学生を対象に2006年から公文式を導入しています。
それまでも子どもたちの学習支援を大切にしていましたが、職員間で差が出てしまう状況があり、個人別に対応できる公文式を導入することになりました。現在は週5日、夕方5時から1時間を「KUMONタイム」とし、小学生が公文の教材に取り組んでいます。
佐々木園長は、100点をとった時の子どもたちの笑顔や達成感あふれる表情を見て、「小さな成功体験を積み重ねることで子どもたちに自信がつく」とおっしゃいます。
また、教材の採点は施設の職員が行っており、子どもたちの学習をサポートしています。発達心理学を専門とする白百合女子大学の田島信元教授は、「施設の職員と子どもたちとの関わりが素晴らしく、この施設におけるKUMONタイムは、子どもたちにとってスタッフの方々と共にがんばる“大切な時間”となっている」とその意義を語ります。
<事例2>
児童養護施設「大村報徳学園」の取り組み

1983年から40年以上にわたり公文式を導入している、鹿児島県の大村報徳学園。同学園での公文式学習の推進役である、岩元次郎先生は、「教室が楽しくて仕方がない」「子どもたちも公文式学習が大好きですが、ここに至る道のりは決して平たんではなかった」と話します。「私が入職した時はすでに導入から5年ほどたった頃で、当時、職員の間で『計算力だけつけてどうするの?学力向上に即効性がないのでは?』という、公文式への不満が起きていた」とのこと。
その後、園舎の建て替えでの学習場所の確保が困難な時期や、部活動との兼ね合いで負担に感じた子どもたちの不満など、継続にあたり困難もあったと話します。「でも私は、公文式学習で伸びる子どもたちを見てきました。児童養護施設に入所してくる子どもたちは、さまざまな事情を抱えてやってきます。公文の教材ができたこと、そしてほめることを繰り返していくと、子どもたちは少しずつ自己肯定感を身につけていくんですね。虐待による発達障害を持った支援学級の子でも、学年を越えてできるように成長していくんです。このことが、岩元先生が同学園での公文式学習を続けていく原動力になった」と話します。
学習進度がわかり、子どもたちの成長が共通認識され、生活面での変化も語られるようになり、職員の間でも、公文式導入の効果とみられる正のスパイラルが生まれるようになったそうです。

また、岩元先生は鹿児島県で公文式を導入している児童養護施設の担当者たちの勉強会である「鹿児島地区会」の牽引役でもあります。20年以上続くこの会では、KUMONを共通言語に、毎回テーマに沿った学び合いやフリートークを通じて各施設における事例や課題などを共有し、熱量をもって情報交換ができる場となっています。地区会に参加されていた各施設の職員の方々からも、「公文式学習のおかげで、子どもたちを認めてあげることが増えました。どうしても日常とか学校のことは個人差が出てきますが、公文だとどの子もすぐにほめる材料を見つけてあげられるかな、と感じています」など、公文式導入の成果について、嬉しいお声をいただいています。
児童養護施設での公文式学習は、創始者が残した「悪いのは子どもではない」の言葉がまさに実践されている場であり、それは各施設の職員の方々の並々ならぬ尽力と、地区会のような場を通じた相互啓発によって支えられているのです。
<事例3>
「ひまわり学園真美ケ丘自立訓練校」の取り組み
奈良県広陵町にある「ひまわり学園真美ケ丘自立訓練校」では、特別支援学校を卒業した障害のある方たちの生活介護サービスが行われています。「自分のできることに自信をもって、他者と関わり合いながらたくましい人生を歩んでいってもらいたい」という理念のもと、2006年3月の開所と同時に公文式学習を導入しました。

現在は平日の週4日、午前中の1時間を使って、算数や国語の教材学習に取り組み、KUMONのカード教具なども活用されています。そんな中で生まれたのが、「自信」と「信頼関係」。
施設長の坂口紀和さんは公文式を導入しようと思った理由について、「訓練生は中・重度の知的・発達障害のある方たちなのですが、地元の特別支援学校では、どうしても『木工』や『農園』といった、卒業後に事業所で通用するものを身につけてもらうことがメインとなり、なかなか『学習』という時間が設けられていないという話を耳にしていました。そこで、『学習』の時間をつくることで、例えば自分の名前を読めたり書けたり、あるいは簡単なお金の計算ができたりすることで自信をつけることが、日常生活にも波及されるのではないかと考えました」と話します。
坂口さんは、自身が中学校3年間KUMONの教室に通い、身を持って学習効果を感じていた元公文生。「何よりも『無理なく』やれるところから、ということを重視しています。一人ひとりの学習の様子を見ながら、『無理なく』に加えて『ちょっとがんばれる』ところはどこなのか、ということを大事にしながら声かけしたり、教材のレベルや学習する枚数を考えたりしています。それは、自分自身が中学生の時にくもんの先生にしていただいたことで、その経験が生かされているかなと思います。もう一つは、あくまでも公文式はツールの一つであって、障害者支援の視点を忘れてはいけないということも、常に職員たちと確認し合っています。一番の目的は、訓練生たち本人の生活が豊かになること。そのことを念頭に置きながらやってきたからこそ、中・重度の知的・発達障害のある訓練生たちにも学習効果が表れてきているのではないかと思っています」と語ります。
特に重度の知的障害のある3人の訓練生について話してくださいました。「この3人はここに来るまでは『ひらがなを書く』『計算をする』といった学習がなかなかできなかったと思います。その理由の一つには、周囲からの『できないだろう』という先入観もあったのではないでしょうか。しかし、公文式学習によって『できるところはどこだろう』ということを探しあてることができたおかげで、学習効果が表れています。現在では、学習時間中は席に座って学習することができている3人ですが、最初は座り続けることも、職員と対面で学習することもままなりませんでした。それが今では自分からカードをめくって、一生懸命、発語しようとすることも見られるようになり、発語や表現方法が少ない訓練生とは、カードを通じて意思疎通が図れたという実感がありました。『○○君はちゃんとわかっているんだ!』ということが、私たち職員にはよくわかりました」。

また、「職員にとっても、訓練生一人ひとりの潜在能力を引き出し、よいところを見つけるツールになっているそうです。また、『じゃあ、次はここまでステップアップできるかな』と、スモールステップで能力を伸ばす楽しさにもつながっています。そうした日々の積み重ねによって、職員たちにも自然と訓練生一人ひとりを「観察する力」や「能力を見抜く力」「ポジティブな視点」が養われているのではないかと考えています。こうした関わりの中で、お互いのモチベーションにもなっていると思いますし、信頼関係を作り出しているのではないかと思います」と坂口さんは語ります。
このように『どんな子どもでも素晴らしい可能性を秘めている。 自分自身の可能性を信じ成長してほしい、公文式の学習を通じて精神面の支援をしたい』この思いのもと、会社設立の年(1962年)、 児童養護施設(当時は「孤児院」)での学習支援は、創始者・公文 公(くもん とおる)自らの働きかけから始まりました。 学習者ひとり一人の学ぶ姿勢・習慣や学力・能力向上を図り、 将来的な自立や自己実現等に寄与することを目指し、施設や学校への導入による学習支援を行っています。